養老保険は貯蓄と保険を兼ねた便利な保険で、年末調整や確定申告で社会保険控除が受けることができます。満期になれば保険金が出ますが、受取人を誰にするかで税金の種類や納税額が変わってきます。養老保険の税金や控除についてよく理解し、損をしないようにしましょう。
養老保険の満期にかかる税金はいくらか

養老保険は生命保険の一種ですが、貯蓄機能と死亡保障がセットになっています。
この養老保険は満期になると、満期保険金を受けとることができます。
それでは満期になった時に保険金を全額受け取れるのか、税金がどのくらいかかるのかを今回のテーマとして解説いたします。
主に次のような内容でご説明いたします。
- 養老保険とは何か?その特徴は?
- 受取人をだれにするかで税金の種類や額が変わってくること
- 養老保険控除を受けるための方法
- 養老保険は相続税対策には適していないこと
- 養老保険を解約する方法
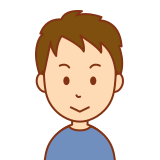
今回「終活.net」では、養老保険の税金について知りたい方のためにあらゆる情報を集め、解説していきます。
お時間がない方でも知りたい情報をピックアップしてお読みいただけます。
ぜひ最後まで目を通していただけると幸いです。
そもそも養老保険とは

養老保険は字の通り「老いを養う保険」で、老後の豊かな生活を送るための保険です。
養老保険は貯蓄を目的としていますが、被保険者が死亡した場合には満期保険金を死亡保険金として受け取ることができます。
養老保険は満期保険金と死亡保険金が同じ金額であり、貯蓄と保険を兼ね備えた商品といえます。
貯蓄を目的としていますので保険料は高めに設定されていますが、満期が到来すればその時まで払い込んだ保険料と利息が上乗せされて支払いが行われます。
保険料の支払いについては毎月積み立てていく方式のものと、一括支払い方式のものがあります。
一括払いの場合には、返戻率だけを考えた場合、保険料が割引になりお得と言えます。
しかし死亡保障を考えた場合には、保険料は全額支払い済みのためメリットはほとんどなく、年払いや月払いのほうがお得と言えます。
養老保険の分類に入る保険には、他には次のようなものが挙げられます。
◎個人年金保険
個人年金保険は民間の生命保険会社が扱っている商品で、預け入れした金額が保険金額となり、一定の年齢になると年金が支払われ、死亡時には死亡保険金か支払われます。
◎学資保険・こども保険
老後の保険ではありませんが、学資保険やこども保険も養老保険に該当します。
子供たちの入学時期に合わせて毎月保険料を支払い教育資金を作ることのできる保険です。
契約期間中に契約者が死亡した場合には以後の保険料の支払いが免除されたり、入学などの節目の時には給付金を受け取ることができるものもあります
養老保険が満期になった時には税金がかかる
生命保険の満期保険金は、被保険者が保険の満期まで生きていた場合に支払われます。
養老保険は生命保険であると同時に、貯蓄を目的としていますので、定期預金と同様に利益については税金がかかることとなります。
税金は支払った保険料全額にかかってくるわけではなく、養老保険の満期時や解約時において、今まで支払った保険料を超えて利益が出た場合にはその利益の部分に税金がかかってきます。
しかし利益がない場合や満期保険金の額によっては非課税となることもあります。
受け取り人で税金の種類がかわる!
保険が満期になった場合や被保険者が病気などで亡くなった場合には、保険金が下りることになります。
その場合には、被保険者及び保険料の負担者・保険金受取人がだれに設定するかによって、所得税か相続税か贈与税か課せられる税金が異なってきます。
◎満期金を受け取った場合
・保険料を支払った人と満期金を受けとった人が同一の場合には所得税がかかります。
これは自分が利益を得るので所得税となります。
・保険料を支払った人と満期金を受け取った人が異なる場合には贈与税がかかります。
これはほかの人に満期金を与えるので贈与税となります。
夫婦子供を例に図表化にすると下記のようになります。
| 保険料負担者 | 保険金受取人 | 税金の種類 |
| 夫 | 夫 | 所得税 |
| 夫 | 妻・子供 | 贈与税 |
◎死亡保険金を受け取った場合
・被保険人と保険料負担者が同一で相続人が受取人の場合相続税がかかります。
・保険料負担者と受取人が同一の場合には所得税がかかります。
・被保険者・保険料負担者・受取人がそれぞれ異なる場合には贈与税がかかります。
夫婦子供を例に図表化すると下記のようになります。
| 被保険者 | 保険料負担者 | 保険金受取人 | 税金の種類 |
| 夫 | 夫 | 妻 | 相続税 |
| 妻 | 夫 | 夫 | 所得税 |
| 妻 | 夫 | 子供 | 贈与税 |
保険料の支払い人=受取人の場合の計算方法
保険金の支払人と受取人が同一の場合で、支払った保険料の合計額よりも満期金のほうが多い場合には所得税がかかります。
満期保険金を一度に受け取った場合には一時所得として所得税の対象となり、年金のように分割して受け取ると雑所得として税金が課せられます。
◎満期金を一度に受け取った場合の税金の計算
納めた保険料を超えた利益の部分について税金がかかるわけですが、50万円までは控除するこ とができます。
さらにその1/2をほかの所得に加えて課税することとなります。
所得税の計算式は下記のようになります
(満期金-支払った保険料の合計-50万円(一時所得の控除額))×1/2
たとえば
満期保険金:1,000万円
保険期間:20年
保険料:月額39,500円
としたときに数式に当てはめると
所得税額=(1,000万円-39,500円×12ヵ月×20年-50万円)×1/2=20,000円
なお、保険金額と払い込んだ保険金との差が50万円以下の場合には、所得税はかかりません。
保険料の支払人≠受取人の場合の計算方法
保険金の支払人と受取人が異なる場合で、支払った保険料の合計額よりも満期金のほうが多い場合には贈与税がかかります。
養老保険で夫が契約者で受取人が妻または子供といった場合には贈与税がかかることになります。
贈与税は所得税よりも高い税率ですので、余分な税金を払うことになりますので注意しなければなりません。
満期受取人をだれにするかはよく考えて契約する必要がありますが、契約者や受取人はいつでも変えることができます。
◎満期金を一度に受け取った場合の税金の計算
贈与税の場合には1年間に受け取った贈与額が110万円までは非課税となり、それを超えた部分は すべて贈与税の対象となります。
贈与税の計算式は下記のようになります
(満期金-110万円)×贈与税率-控除額
たとえば先ほどと同様に
満期保険金:1,000万円
保険期間:20年
保険料:月額39,500円
としたときに数式に当てはめると
贈与税額=(1,000万円-110万円)×税率-控除額
1,000万円以下の場合には税率は40%、控除額は125万円ですので231万円が税額となります。
いかがですか?
保険金の受取人をだれにするかで納める税金が大きく異なると、よく考えて契約する必要がありますね!
養老保険の控除をうけるには
生命保険に入り保険料を支払っていると、生命保険料控除の対象となり税金を安くすることができます。
貯蓄性の有無については問われませんので、養老保険の保険料も控除の対象とすることができます。
給与所得者は年末調整で、自営業者は確定申告で手続きを行い控除を受けます。
年間所得額から1年間に支払った保険料の一定額を差し引き、税金を安くできます。
生命保険料控除は平成22年に改正されました。
◎旧契約における生命保険控除
平成23年12月31日までに契約した保険で、一般の生命保険料控除と個人年金保険料控除の2種類あり、それぞれ最高5万円づつ合計で10万円控除することができます。
なお住民税についてはそれぞれ3万5000円で、合計7万円を控除できます。
◎新契約における生命保険控除
平成24年1月1日以降に契約した保険で、一般の生命保険料控除と介護医療保険料控除・個人年金保険料控除の3種類あり、それぞれ最高4万円づつ合計12万円控除することができます。
なお住民税はそれぞれ2万8000円で、合計8万4000円を控除できます。
なお、一時払いで契約した場合は、加入した年のみ控除の対象とすることができます。
生命保険控除は給与所得者は年末調整で、自営業者は確定申告で申請することになります。
年末調整での控除
年末調整は給与所得者は毎年年末に行いますが、何のために行うのかわからない人もいると思います。
毎月の給料からは所得税が差し引かれますが、年末に年間に支払った所得税額の過不足を精算しますが、これを年末調整と言います。
給料から天引きされる所得税は、生命保険料や地震保険料などは控除されていません。
そこで年末調整をおこなうことで、正確な所得税額を計算し精算することになります。
なお、年末調整ができなかった給与所得者や、自営業者については確定申告で控除の申請を行います。
確定申告での控除
確定申告は自営業者の所得税の納め方で、年間の所得をすべて計算し所得税額を確定し申告する手続きを言います。
給与所得者は毎月の給与から源泉徴収され年末調整を行いますが、自営業者は翌年の2/16~3/15の間に確定し納税しますので、後払いということになります。
確定申告では、所得税の払い過ぎの場合には返してもらうことができますが、これを還付申告と言います。
また多忙等で年末調整の書類を提出でいなかった給与所得者も、確定申告で還付手続きをすることできます。
なお、次にあげる給与所得者も確定申告をする必要があります。
・給与収入が2,000万円以上の人
・2ヶ所以上の会社から給料をもらっている人や副収入があり人で副収入が0万円を以上の人
・個人企業の社員などで源泉徴収が行われていない人
確定申告の書き方
年末調整で生命保険料控除を受けなかっ給与所得者は、確定申告することにより所得税が還付されますが、申告の方法は次のとおりです。
まず税務署より確定申告書第一表・第二表を入手します。
申告書は郵送或いは取りに行きますが、近年はネットで申告する方法も増えてきました。
確定申告の書き方は下記のとおりです。
- 生命保険料控除証明書を集め年間支払額を合計します。
- 第二表の生命保険料控除欄に支払った保険料を記入します。(新旧の契約に合わせ記入)
- 第一表の生命保険料控除欄に2で計算した控除額を計算します。
法人が養老保険の契約者になる場合
法人が契約者になる場合、
受け取りに関しては個人と変わりがありませんが、その場合のお金の動きについてお書きください。
養老保険には、役員や従業員を被保険者とし、法人が契約するものがあります。
福利厚生の一環として利用している法人一般的です、死亡したした場合の保険金受取人、及び満期の場合の保険金受取人の設定の仕方により経理処理の方法が変わってきます。
法人及び被保険者にとってのメリット・デメリットについて解説をいたします。
まとめますと下記のとおり3つのタイプに分けられます。
| タイプ | 被保険者 | 満期受取人 | 死亡金受取人 | 保険料処理 |
| 1 | 役員等 | 法人 | 法人 | 全額資産計上 |
| 2 | 役員等 | 被保険者 | 被保険者の親族 | 全額給与計上 |
| 3 | 役員・従業員 | 法人 | 被保険者の親族 | 1/2資産計上 1/2支払保険料計上 |
法人が保険金の受取人の場合
タイプ1
被保険者が役員等で死亡保険金及び満期保険金の受取人が法人の場合の保険料の経理処理は全額資産に計上します。
・メリット
保険料により資金積立を行うことができ、被保険者に何かがあった場合にはの保障金を出すことができます。
いずれも法人が保険金を受け取ることができ、保険金が掛け捨てになりません。
・デメリット
保険料は保険積立金という勘定科目で資産計上を行い、法人税支払い後に内部留保した資金で支払う形となります。
貯蓄性のある生命保険ですので高額な保険料を支払わなければなず、お金の流れが悪化しますので資金繰りには注意しなければなりません。
被保険者又はその遺族が受取人の場合
タイプ2
被保険者が役員等で死亡保険金受取人が被保険者の親族で満期保険金受取人の被保険者場合の保険料の経理処理は全額給与に計上します。
・メリット
保険料を給与とし損金として計上することができ、法人税負担額が減少します。
法人が保険料を支払いますので、被保険者の負担がありません。
・デメリット
支払保険料は所得として被保険者に加算され、所得税や住民税がかかってくることになります。
法人には保険料の負担になります。
死亡保険金と生存保険金の受取人が違う場合
死亡保険金の受取人が被保険者の遺族で、生存保険金の受取人が法人の場合
タイプ3
被保険者が役員・従業員で死亡保険金の受取人が被保険者の親族、満期保険金の受取人が法人の場合には、支払保険料は 1/2は資産に1/2は保険料に計上 します。
・メリット
保険料の半分を損金として計上できますので、利益が減ることで法人税が減少します。
もしもの場合には役員・従業員に保険金が遺族に支払われますので、福利厚生の一環とすることができます。
また同時に積み立てができるメリットがあります。
・デメリット
役員及び従業員を対象としますので、保険を掛ける旨の説明と署名・捺印・健康状態のチェックを行わねばなりません。
社員の過半数が対象の必要があり、社員が多い場合には作業が大変です。
加入者が死亡後の受け取りは?
死亡保険金の受取と、その後の税金についてお書きください。
「死亡保険金」の受け取りにかかる税金
前述のように養老保険の加入者が死亡した時には、保険金が支払われます。
その際契約者及び被保険者・受取人をだれにするかによって税金の種類が変わってきます。
・契約者と被保険者が同一で受取人が違う場合には相続税がかかってきます。
しかし相続税には配偶者の税額軽減や未成年者控除・基礎控除・生命保険の非課税などがありますので、税金がかからない場合がほとんどです。
・契約者と受取人が同一で被保険者が異なる場合には所得税の対象となります。
この場合には一時所得となりますので保険金額から保険料を引きさらに50万円を引いた額が所得税課税対象となります。
・契約者と受取人が同一で被保険者が異なる場合には贈与税の対象となります。
贈与税の場合には保険金から110万円しか控除できませんので、税金が多くかかることとなります。
従いまして、受取人をだれにするか注意が必要です。
養老保険は相続対策にはならない
生命保険は相続税対策としては非常に有効的ですが、養老保険は不向きと言われます。
養老保険は生命保険と同時に貯蓄を目的としていますので、満期になると保険金が支払われます。
生命保険には遺産分割対策、納税資金対策、節税対策があるとされます。
・遺産分割対策は、死亡保険金の受取人を指定できますので、遺産分割協議の対象外とすることができます。
・納税資金対策は相続が起きた時に保険金をすぐに現金化することができ、葬儀費用や不動産の名義を変えることなどに利用できます。
・相続税対策は(相続人の数×500万円)を非課税財産として控除できますので相続財産を減額することができます。
養老保険では満期までは相続対策となりますが、満期になると現金になってしまいますので生命保険のメリットを生かすことができなくなります。
それゆえ相続対策としては不向で、相続対策としては終身の死亡保険が有利ということができます。
このように相続は複雑な部分も多く、不安も大きいのではないでしょうか。
一人で考えるより、相続に詳しいプロの方などに相談することで、新たな気づきがあるかもしれません。
「終活ねっと」には相続に関する無料ご相談窓口があります。
提携している相続診断士やファイナンシャルプランナーが遺言や生前対策など相続全般に関するご相談を伺います。
ご相談は初回無料ですので、些細な疑問でも下記のリンクから気軽にご相談ください。
養老保険を解約するには
養老保険を解約するには証書や印鑑・身分を証明するものなどを持って手続きをします。
養老保険は定期保険とは異なり貯蓄型の保険ですので、途中解約をした場合には終身保険と同様に保険料が払い戻されます。
これを解約返戻金と言います。
近年、解約返戻金がない無解約返戻金型や解約返戻金を抑えた低解約返戻金タイプもでき保険料が低い反面解約をすると損ということができます。
解約にあたっての注意点
・解約した場合には支払った保険料よりも少ない金額になります。
特に契約~解約するまでの期間が短いと、保険料の支払い額に対して返戻率は低くなります。
逆に払込期間が長ければ返戻率は高くなりますので、極力満期まで継続したほうがよいでしょう。
・将来再契約の場合には年齢も高くなり、保険料が高くなります。
・保証が無くなったり、生命保険料控除や相続税の特典だなど受けられなくなります。
解約返戻金
解約返戻金の計算方法は下記の計算式で表されます。
解約返戻金=(保険料総額-(加入期間の保険料+保険会社のコスト等))×運用益
一般的に30年契約で10年払い込んだ場合には、満期返戻金の90%に満たない額となります。
養老保険と税金まとめ
いかがでしたか?
今回終活.netでは、養老保険について解説しました。
まとめると以下のようになります。
- 養老保険は貯蓄と死亡保障がセットになった保険で、満期になった場合と被保険者が死亡した場合には同額受け取ることができること
- 死亡保障を考えた場合には毎月積み立てが得で、一括払いの場合は保険料の割引があること
- 満期になった時には税金がかかり受取人を誰にするかにより税金の種類と額が変わること
- 満期金の場合には保険料負担者と保険金受取人が同一の場合には所得税がかかり、異なる場合には税率の高い贈与税がかかること
- 死亡保険金の場合には保険金受取人が妻の場合には相続税がかかること
- 養老保険も生命保険料控除の対象となりますので年末調整または確定申告で手続きを行うこと
- 養老保険は貯蓄を目的としていますので相続税対策には向いていないこと
養老保険は月々の保険料は多少高いですが、生命保険と貯蓄を兼ね備えているメリットがあります。
下記に養老保険についてまとめましたので、メリット・デメリットを考え上手利活用するようにしましょう。
最後までお読みいただきありがとうございました。



コメント