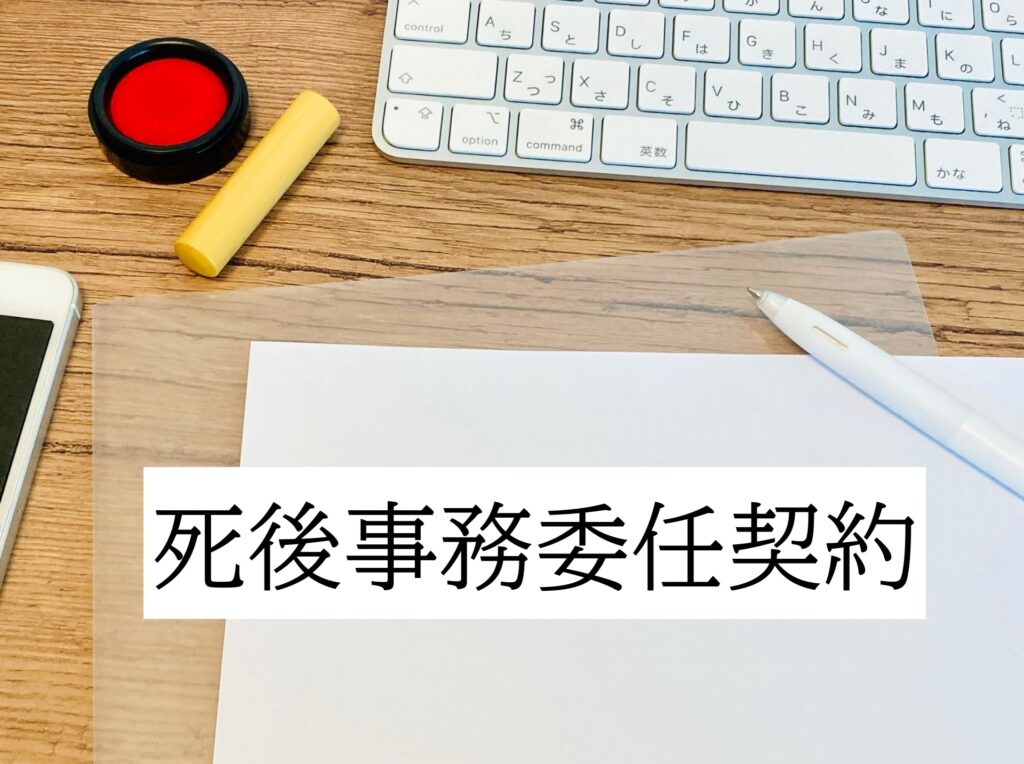
お一人様とは
近年の日本はついに100歳以上の人口が8万人を超える長女高齢社会となり、頼れる親族のいない単身世帯も大変増えています。
深刻な事態としては高齢者のお一人様が増えています。
(お一人様とは同居する人がいない状態のことを言います)
お一人様になる理由は、障害や、独身の人や、死別離別など様々です
また、一人暮らしをする65歳以上の人様も増えています
このような社会背景から、死後事務委任契約の必要性が生じていると言えます。
人が亡くなってしまうと、その後の手続きはどのように進むのでしょうか
人が亡くなると、葬儀をはじめとして、亡くなるまでにかかった医療費や公共料金の支払い、年金受給の停止など様々な手続きをする必要が出てきます
これらの事務手続きを死後の事務と呼び、通常は亡くなった人の親族が行うのが一般的です。
しかし亡くなった人に身寄りがなかったりあっても疎遠だったりした場合はそれの手続きをする人がいません。
死後事務委任契約とは、死後に発生する相続手続き以外の事務処理を、信頼できる人に任せておける生前準備の一つです。
委任内容は非常に幅広く、周囲の人の手を煩わせがちな死亡届等の提出、葬儀の手配、関係者への連絡から、遺品処分に関する注文まで細かく指定することができます。
だったら遺言書を利用すればいいのではないかと考える人もいるかもしれません
しかし死後の事務は遺言書に記載したとしても法律上の効力はなく実際的ではありません
理由についてはこちらの記事で解説しておりますのでお時間がある時にご覧
ください
その点、死後の事務委任契約を結んでおくと、手続きをする人がいなくて困るといったリスクを避けることができます。
死後の事務委任契約とは、このような場合の手続きを行う人と内容について事前に決めておく契約だからです。
死後の事務は誰が行ってくれるのでしょうか
さて、お一人様の場合、身寄りのない方が亡くなった場合の死後事務は、市区町村で行うと思っていらっしゃる方がいますが、これはほとんどが間違いです。
例えばホームレスの方が路上で亡くなったケースと同じで、身寄りのない方が亡くなった場合でも、遺体については市区町村で火葬してもらえます。
しかし、これは、あくまで遺体をそのままにしておくわけにはいかないための処置であり、火葬の前に葬儀をあげてくれたり、遺品整理を市区町村が代わりに行ってくれるということではありません。
ですので、最終的にはお国が何とかしてくれるという考え方は間違いであって、何も準備をせずにいると、万が一の時に周りに多大な迷惑と負担を強いることになってしまいます。
お一人様が亡くなってしまうと、ご遺体はどうなるのでしょうか
万が一死亡した場合自分の遺体はどうなるのでしょうか?
死亡した場所や状況によって遺体の取り扱いが変わります
近年増加している高齢者の孤独死のケースですと、まずは警察によって死亡に事件性がないのか調査をされた後に、遺族との調査が行われ、遺族がいる場合は引き渡しをされます
身寄りのない高齢者の場合は、市区町村にて民生葬として直葬等で火葬されることになりますが、すぐに火葬されるとは限りません。
身寄りがないと言ってもそれはなくなった状況から判断しているだけで、実際にお子様や兄弟がいるかもしれません。
当然、市区町村でも、そうした方がいる可能性を考えて、すぐに活動するわけではなく、一旦警察や葬儀社の遺体安置室にて、ご遺体を安置し、その間に相続人や親族を探すこととなります
親族がすぐに見つかり、対応を引き受けてくれれば問題はありませんが、親族間でトラブルなどが起きたりすると、決着がつくまで、遺体は、安置室などに置かれたままになってしまい、場合によっては死後1年近く安置されているようなケースもあります
こうした状況を避けるためにも自分に万が一のことがあった場合に、それに対応してくれる人を事前に決めておいたり必要に応じて死後事務委任契約書などで、ご遺体の引き取りや、葬儀の手配をしてくれる方を決めておくと、誰にも迷惑かけずに死後の手続きを進めることが可能となります
遺品整理は誰が行ってくれるのでしょうか
自分に万が一のことがあった場合に自分の部屋は誰が片付けてくれるのでしょうか?
賃貸であれば、実際に死後の備えを何もしてなければ、大家さんをはじめ水道光熱費や電話会社などに迷惑をかけることになります
身寄りのない方のケースですと、親族がいないまたはいても協力は仰げないといった状況が多く、当然遺品整理の手配や費用の年数などは期待できません
そうした場合の多くが、個人の室内に残った家財類は、誰も片付けるものもなくそのまま放置されてしまうこととなります
こうした場合は、大家さんや管理会社によって、室内の明け渡し手続きを行ったり、入居者が孤独死した場合や家賃を滞納した場合に備えて保険や保証会社と提携しているケースもありますので、こうした制度を利用しながら室内の家財を整理していくことになります
ただしこれは大家さん側としては何のメリットもなくできれば避けたい状況でもありますので、自分に万が一のことがあった場合に備えて、家族や親族に代わって遺品整理等を行い、部屋を明け渡ししてくれる方を決めておくのが最善となります
いずれにしても市区町村で行う死後事務は最低限のことだけであり、遺品整理や財産整理などは一切行ってくれないのが実情ということですね
生活保護を受けている場合は自治体で死後事務を行ってくれるのでしょうか
これまでも述べている通り国や地方自治体は身寄りのない方の火葬はしてくれますが死後事務までは行ってくれません
これは生前に自治体から生活保護を受けていた方も同様で、医療費などが無料になるのだから葬儀や死後事務をすべて自治体が面倒を見てくれるだろうというのは甘い考えです
たとえ生活保護を受けていた方でも、死後事務を国や自治体が行ってくれるということはありませんので、ご自身で準備をしていく必要があります
生活保護を受けている方ができる事前の準備はあるのでしょうか?
とはいえ生活を向けている方の場合は日常の生活だけでギリギリということもあり、身元保証契約や死後事務などを、第三者に依頼したくても利用料を捻出できないということも考えられます
でもこれまでお伝えしている通り、自分がこのまま死んでしまったとしても国や自治体は死後事務を行ってくれないし、特に賃貸物件で生活しているような場合は遺品整理を行ってくれる方がおらず、長年お世話になった大家さんに迷惑をかけてしまうかもしれないとそんな不安がありますよね
確かに利用料が支払うことができず、民間のサービスを利用できないということは考えられます
しかしだからといって何もできないっていうわけではありません。
生活保護を受けているご本人が何も準備せずになくなってしまうと、賃貸物件の大家さんは個人の荷物を勝手には処分できません
相続人がいるかもしれませんし、相続人がいない場合でも本来は相続財産管理人の選任申請を裁判所に行った上で手続きを進めていくのが本来の道筋です。
遺品整理が完了するまでに多大な能力と時間費用を費やすことになってしまいます
でも事前に本人と大家さんとの間で死後事務委任契約書のようなしっかりとした書面ではなくて、念書や合意書のような簡単なものでも構わないので、「入居者が亡くなった場合は入居者の家財処分を死後に一任する」といったような文章を一筆差し入れておくだけで、家主側としては正当な権利の下で遺品整理を行うことができるようになるではないでしょうか
実際の費用などは大家さんの持ち出しになってしまうかもしれませんが、次の募集までの期間を短くすることが可能となり、難しい手続きで頭を悩ます必要がなくなるだけでも、大家さんにとっては助かります。
あとは、本人自身が日常生活でゴミを溜めず、掃除も適度に行っておくことで、大家さんの負担はぐっと下がります。
できる範囲での準備を心がけましょう。
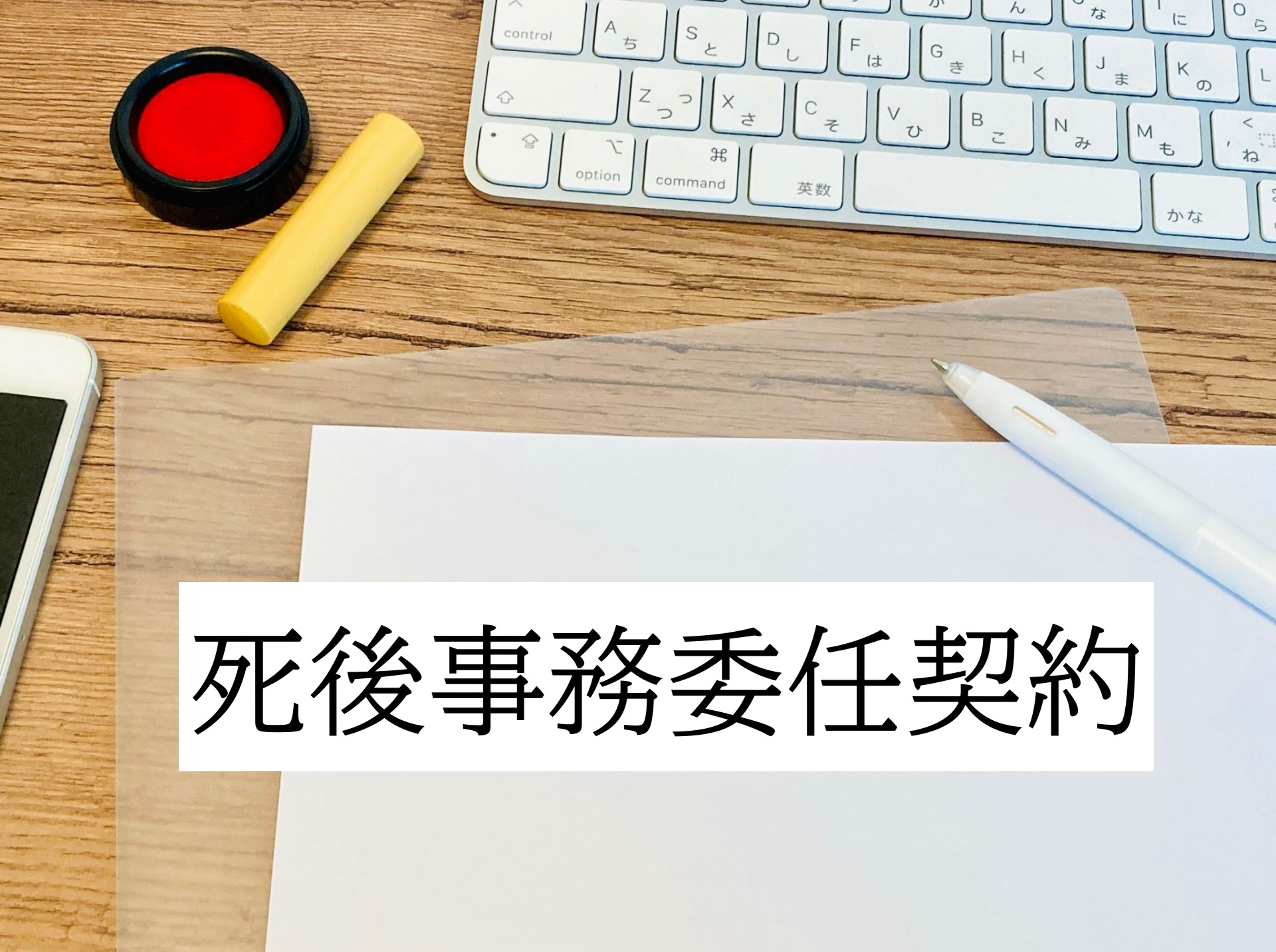


コメント